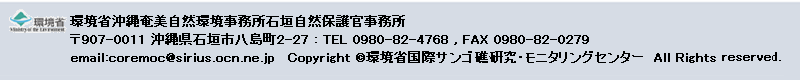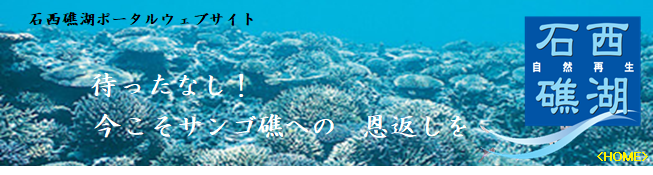
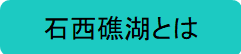
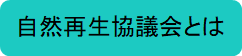
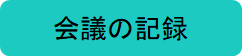
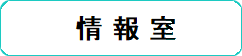
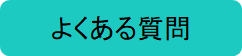








石西礁湖自然再生ニュースレター
 ニュースレター第27号(2.1MB) ★2020年の石西礁湖 ★石西礁湖自然再生協議会は第8期に入りました ニュースレター第27号(2.1MB) ★2020年の石西礁湖 ★石西礁湖自然再生協議会は第8期に入りました
|
 ニュースレター第26号(2.1MB) ★サンゴ幼生の加入量の状況 ★環境省事業実施計画が承認 ニュースレター第26号(2.1MB) ★サンゴ幼生の加入量の状況 ★環境省事業実施計画が承認
|
 ニュースレター第25号(2.2MB) ★2019年の石西礁湖 ★第25回協議会 ★環境省の新しい事業実施計画の検討 ニュースレター第25号(2.2MB) ★2019年の石西礁湖 ★第25回協議会 ★環境省の新しい事業実施計画の検討
|
 ニュースレター第24号(2.4MB) ★2018年の石西礁湖 ★第24回協議会 ★行動計画の進め方 ニュースレター第24号(2.4MB) ★2018年の石西礁湖 ★第24回協議会 ★行動計画の進め方
|
 ニュースレター第23号(.02MB) ★2017年の石西礁湖 ★行動計画2019-2023 ★協議会第7期の体制 ニュースレター第23号(.02MB) ★2017年の石西礁湖 ★行動計画2019-2023 ★協議会第7期の体制
|
 ニュースレター第22号(4MB) ★2016年夏の大規模白化の影響 ★石西礁湖自然再生事業の検証と今後の進め方 ニュースレター第22号(4MB) ★2016年夏の大規模白化の影響 ★石西礁湖自然再生事業の検証と今後の進め方
|
 ニュースレター第21号(2.5MB) ★2016年夏の大規模白化のその後 ★サンゴの大規模白化現象に関する緊急宣言 ニュースレター第21号(2.5MB) ★2016年夏の大規模白化のその後 ★サンゴの大規模白化現象に関する緊急宣言
|
 ニュースレター第20号(1.2MB) ★2016年夏の大規模白化に関する話題提供と意見交換 ニュースレター第20号(1.2MB) ★2016年夏の大規模白化に関する話題提供と意見交換
|
 ニュースレター第19号(2.5MB) ★石西礁湖の近年の状況 ★目標達成に向けて取り組んだこと ★第19回協議会 ニュースレター第19号(2.5MB) ★石西礁湖の近年の状況 ★目標達成に向けて取り組んだこと ★第19回協議会
|
 ニュースレター第18号(1.4MB) ★最近数年間はサンゴが回復する傾向に ★わくわくサンゴ石垣島プロジェクト ニュースレター第18号(1.4MB) ★最近数年間はサンゴが回復する傾向に ★わくわくサンゴ石垣島プロジェクト
|
 ニュースレター第17号(2.4MB) ★石西礁湖の近年の状況 ★石西礁湖自然再生全体構想:短期目標10年 ニュースレター第17号(2.4MB) ★石西礁湖の近年の状況 ★石西礁湖自然再生全体構想:短期目標10年
|
 ニュースレター第16号(4.0MB) ★協議会の多様な主体の取組状況 ★ワーキンググループの活動報告 ニュースレター第16号(4.0MB) ★協議会の多様な主体の取組状況 ★ワーキンググループの活動報告
|
 ニュースレター第15号(4.9MB) ★オニヒトデ対策 ★協議会の体制が変わります ★サンゴ礁基金による助成活動 ニュースレター第15号(4.9MB) ★オニヒトデ対策 ★協議会の体制が変わります ★サンゴ礁基金による助成活動
|
 ニュースレター第14号(3.8MB) ★サンゴの病気が広がっています ★協議会新体制への提案 ★ヨナラ水道 ニュースレター第14号(3.8MB) ★サンゴの病気が広がっています ★協議会新体制への提案 ★ヨナラ水道
|
 ニュースレター第13号(7.4MB) ★移植サンゴの産卵を確認! ★石西礁湖サンゴ礁基金の助成活動始まる ニュースレター第13号(7.4MB) ★移植サンゴの産卵を確認! ★石西礁湖サンゴ礁基金の助成活動始まる
|
 ニュースレター第12号(6.3MB) ★協議会委員の1年 ★石西礁湖サンゴ礁基金の使途と仕組み ニュースレター第12号(6.3MB) ★協議会委員の1年 ★石西礁湖サンゴ礁基金の使途と仕組み
|
 ニュースレター第11号(6.3MB) ★サンゴは増えているか? ★石西礁湖自然再生行動指針 ★赤土流出 ニュースレター第11号(6.3MB) ★サンゴは増えているか? ★石西礁湖自然再生行動指針 ★赤土流出
|
 ニュースレター第10号(3.1MB) ★平成20年度のオニヒトデ発生状況 ★第10回協議会 ★八重山サンゴカフェ ニュースレター第10号(3.1MB) ★平成20年度のオニヒトデ発生状況 ★第10回協議会 ★八重山サンゴカフェ
|
 ニュースレター第9号(3.6MB) ★石西礁湖周辺のサンゴ礁の現状と今後の展望 ★国際シンポジウム開催 ニュースレター第9号(3.6MB) ★石西礁湖周辺のサンゴ礁の現状と今後の展望 ★国際シンポジウム開催
|
 ニュースレター第8号(1.8MB) ★第8回協議会 ★石西礁湖自然再生事業環境省事業実施計画の概要 ニュースレター第8号(1.8MB) ★第8回協議会 ★石西礁湖自然再生事業環境省事業実施計画の概要
|
 ニュースレター第7号(1.8MB) ★第7回協議会 ★国際サンゴ礁2008 ★2007年オニヒトデ発生状況 ニュースレター第7号(1.8MB) ★第7回協議会 ★国際サンゴ礁2008 ★2007年オニヒトデ発生状況
|
 ニュースレター第6号(2.2MB) ★第6回協議会 ★記念シンポジウム ★石西礁湖自然再生事業の実施に向けて ニュースレター第6号(2.2MB) ★第6回協議会 ★記念シンポジウム ★石西礁湖自然再生事業の実施に向けて
|
 ニュースレター第5号(6.2MB) ★第5回協議会 ★石西礁湖自然再生全体構想 ★沖縄の港湾におけるサンゴ礁調査 ニュースレター第5号(6.2MB) ★第5回協議会 ★石西礁湖自然再生全体構想 ★沖縄の港湾におけるサンゴ礁調査
|
 ニュースレター第4号(3.7MB) ★第4回協議会 ★石西礁湖自然再生に向けた取組 ★エコツアー ニュースレター第4号(3.7MB) ★第4回協議会 ★石西礁湖自然再生に向けた取組 ★エコツアー
|
 ニュースレター第3号(3.3MB) ★第3回協議会 ★石西礁湖自然再生全体構想 ★サンゴの白化現象 ニュースレター第3号(3.3MB) ★第3回協議会 ★石西礁湖自然再生全体構想 ★サンゴの白化現象
|
 ニュースレター第2号(3.8MB) ★第2回協議会 ★取組と役割分担 ★海の自然教室 ★オニヒトデ ニュースレター第2号(3.8MB) ★第2回協議会 ★取組と役割分担 ★海の自然教室 ★オニヒトデ
|
 ニュースレター第1号(4.3MB) ★第1回協議会 ★石西礁湖サンゴ礁の現状 ★赤土流出対策 ニュースレター第1号(4.3MB) ★第1回協議会 ★石西礁湖サンゴ礁の現状 ★赤土流出対策
|
協議会へご参加
| 協議会へご参加希望の方はこちらをご覧ください | |
 石西礁湖自然再生協議会規約(260KB) 石西礁湖自然再生協議会規約(260KB) |
|
 参加応募用紙(個人)PDF版 参加応募用紙(個人)PDF版 |
 参加応募用紙(個人)Word版 参加応募用紙(個人)Word版 |
 参加応募用紙(団体)PDF版 参加応募用紙(団体)PDF版 |
 参加応募用紙(団体)Word版 参加応募用紙(団体)Word版 |
 登録変更用紙(個人)PDF版 登録変更用紙(個人)PDF版 |
 登録変更用紙(個人)Word版 登録変更用紙(個人)Word版 |
 登録変更用紙(団体)PDF版 登録変更用紙(団体)PDF版 |
 登録変更用紙(団体)Word版 登録変更用紙(団体)Word版 |
資料室
子どもサンゴ礁楽会・紙芝居
環境省では、サンゴ礁の保全に向けた普及啓発として、平成17年11月2日に八重山地域の小学生を対象に「子どもサンゴ礁楽会」を開催しました。
伊野田小学校、崎枝小学校、吉原小学校のこども達29人が、3・4年生、5年生、6年生の3つのグループに分かれ、「サンゴのある海で起こっている問題」、「解決方法」、「将来こうあって欲しいと思うサンゴのある海の姿」、そして「そのために自分たちにできること」を考え、それを物語にして、紙芝居を作り、発表しました。
フィールドワーク
シンポジウム
平成15年11月16日に、石西礁湖の自然再生は、計画の策定段階から地域に皆さん、ボランティア、NPO、専門家、地方公共団体、環境省など国の機関などサンゴ礁の海にかかわりを持つ多様な主体の参加と協力で実施していきます。そのため、調査結果を広く知っていただくための説明会、マスタープラン作りに提案をいただく意見交換会、サンゴ礁の現状を広く知ってもらうためのシンポジウムや講演会を開催していきます。 …詳細
石西礁湖自然再生フォーラム
平成17年7月3日に、八重山の豊かな海をよりよい形で将来の世代に伝えていくために、サンゴ礁に囲まれた島に暮らす皆さん、専門家、環境省など行政機関が一緒に考え、行動していく場として「自然再生協議会」を設置します。自然再生協議会には、この八重山の豊かな海ために一緒に活動する方であればどなたでも参加することができます。 …詳細
講演会「石西礁湖はすごかった-考えよう、私たちの海のこと」
平成18年11月17日に、石西礁湖自然再生協議会主催による「石西礁湖はすごかった ‐ 考えよう、私たちの海のこと ‐」が石垣市で開催され、井田齊氏(株式会社プレック研究所 生態研究センター長)と池田 元氏(海人、沖縄県指導漁業士)のお二方にご講演いただきました。 …詳細
サンゴ移植地見学会が開催されました
平成18年11月18日に、石西礁湖自然再生協議会主催による「サンゴ移植地見学会」が行われました。
サンゴ移植地見学会は石西礁湖でサンゴの再生事業が行われている新城島、黒島に船で行き、サンゴの着床具の見学やCOD(水の汚れを表す指標)の簡易調査などを行いました。
…詳細
第1回サンゴ礁保全ワークショップ
平成16年11月21日に第1回目のワークショップを開催しました。このワークショップでは、24名の参加者の方々が3つのグループに分かれ、「石西礁湖のサンゴ礁の将来あるべき姿」の検討をゴールイメージとして設定し、以下の流れに沿ってグループワーク(作業)を展開しました。 …詳細
第2回サンゴ礁保全ワークショップ
平成17年1月29日に第2回目のワークショップを開催しました。今回のワークショップには、一般の市民のほかダビング事業者と漁業者の参加もあり、総勢31名で始まりました。今回はサンゴ礁を取り巻く様々な環境を原点から見つめ直し、各主体の日常的な生活の視点から解決方法を探ってみようと考え、テーマを2つ設定して、ワークショップを展開しました。 …詳細
報告書アーカイブ
サンゴ礁修復に関する技術手法 - 現状と課題 -
| 報告書名 | サンゴ礁修復に関する技術手法 - 現状と課題 - |
| 年月 | 平成15年11月 |
| 作成元 | 環境省自然環境局、大森信編著 |
| 目的 | 本書は、今後荒廃したサンゴ礁において移植等によるサンゴ礁修復の幼生が高まることを想定し、各地でサンゴ礁修復の事業が行われる際にさんこうとなるよう、それぞれの研究と事業で主要な役割を果たした方々に成果と既往の知見をとりまとめてもらい作成したものである。 |
| 項目 |
|
| 結果 |
※「Manual for restoration and remediation of coral reefs」は、上記書物の英語版である。
報告書
 サンゴ礁修復に関する技術手法 (2,035 KB) サンゴ礁修復に関する技術手法 (2,035 KB)
|
 Manual for restoration and remediation of coral reefs (1,831 KB) Manual for restoration and remediation of coral reefs (1,831 KB)
|
平成19年度 石西礁湖オニヒトデ分布調査
| 報告書名 | 平成19年度 石西礁湖オニヒトデ分布調査 |
| 年月 | 平成19年12月 |
| 作成元 | 環境省那覇支援環境事務所、株式会社イーエーシー |
| 目的 | 本調査では、サンゴ群集のかく乱要因として監視すべきオニヒトデについて、簡易モニタリング調査により分布状況を把握し、対応策の検討を行うことを目的とする。 |
| 項目 |
|
| 結果 |
報告書
 平成19年度 石西礁湖オニヒトデ分布調査報告書 (1,909 KB) 平成19年度 石西礁湖オニヒトデ分布調査報告書 (1,909 KB)
|
平成19年度 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動事業報告書
| 報告書名 | 平成19年度 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動事業報告書 |
| 年月 | 平成20年3月 |
| 作成元 | 八重山漁業協同組合 |
| 目的 | 本事業では、昨年度まで海中公園地区のみで行われてきたサンゴ礁保全活動(オニヒトデ駆除)を、これまで石西礁湖自然再生事業で実施されていた地域(オニヒトデに対する重点地域)を含めた地域で実施することを目的とした。 |
| 項目 |
|
| 結果 |
報告書
 平成19年度 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動事業(石西礁湖オニヒトデ駆除業務)報告書 (1,032 KB)
平成19年度 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動事業(石西礁湖オニヒトデ駆除業務)報告書 (1,032 KB)
|
平成16年度 西表国立公園石西礁湖及び近隣海域におけるサンゴ礁モニタリング調査 報告書
報告書
 平成16年度 西表国立公園石西礁湖及び近隣海域におけるサンゴ礁モニタリング調査報告書 (3,495 KB) 平成16年度 西表国立公園石西礁湖及び近隣海域におけるサンゴ礁モニタリング調査報告書 (3,495 KB)
|
平成17年度 石西礁湖サンゴ群集変動調査
報告書
 平成17年度 石西礁湖サンゴ群集変動調査報告書 (3,912 KB) 平成17年度 石西礁湖サンゴ群集変動調査報告書 (3,912 KB)
|
平成18年度 持続可能な漁業・観光利用調査
(石西礁湖自然再生事業)
報告書
 平成18年度 持続可能な漁業・観光利用調査 (9,922 KB) 平成18年度 持続可能な漁業・観光利用調査 (9,922 KB)
|
サンゴ幼生着床具を用いたサンゴ群集修復マニュアル
(平成18年度 石西礁湖自然再生施設サンゴ群集修復(サンゴ移植)工事管理業務 報告書)
| 報告書名 | サンゴ幼生着床具を用いたサンゴ群集修復マニュアル (平成18年度 石西礁湖自然再生施設サンゴ群集修復(サンゴ移植)工事管理業務 報告書) |
| 年月 | 平成19年3月 |
| 作成元 | 環境省九州地方環境事務所那覇自然環境事務所 |
| 目的 | 平成17年度より、環境省ではサンゴ幼生着床具を用いたサンゴ群集修復事業を実施しており、本事業は今後発展的に展開していくことが予想されるが、事業の拡大に伴い携わる技術者の増加が必要となってくる。そのため、本書では、これまでに得られた知識と経験に基づき、着床具を用いて移植を行う技術手法についてまとめることを目的とする。 |
| 項目 |
|
| 結果 |
|
報告書
 平成18年度 石西礁湖地区自然再生施設サンゴ群集修復(サンゴ移植) 工事管理業務報告書 サンゴ幼生着床具を用いたサンゴ群集修復マニュアル (4,905 KB) 平成18年度 石西礁湖地区自然再生施設サンゴ群集修復(サンゴ移植) 工事管理業務報告書 サンゴ幼生着床具を用いたサンゴ群集修復マニュアル (4,905 KB)
|
平成18年度 石西礁湖自然再生技術手法検討調査業務 報告書
報告書
 平成18年度 石西礁湖自然再生技術手法検討調査業務報告書 (33,961 KB) 平成18年度 石西礁湖自然再生技術手法検討調査業務報告書 (33,961 KB)
|
リンク集
| 環境省 | 竜串自然再生協議会 |
| 国土交通省の自然再生事業 | 阿蘇草原再生協議会 |
| 釧路湿原自然再生協議会 | 竹ヶ島海中公園自然再生協議会 |
| サロベツ自然再生事業 |
自然再生事業の解説
| 自然再生推進法とは | 生物多様性関連情報 |
環境影響評価関連
| 環境影響評価情報支援ネットワーク |
関連行政
| インターネット自然研究所 (環境省自然環境局) |
生物多様性情報システム (環境省自然環境局生物多様性センター) |
| 環境省自然環境局 | 九州地方環境事務所 |
| 子供パークレンジャー |
用語集
あ
- アーサ
- 沖縄の方言で、和名はヒトエグサという緑藻。春先にサンゴ礁の浅瀬に繁殖するアーサーをおばぁ達が採る光景は、昔から沖縄の島々の風物詩になっている。採れたアーサーはお汁などに入れて食べられる。
赤土 - 赤褐色、赤黄色を呈する酸性の風化土壌。沖縄では、国頭マージ、島尻マージと呼ばれる。
安定同位体 - 同じ原子番号を持つが、質量数が異なる原子で、放射線を出さないもの。
ICRI - 国際サンゴ礁イニシアティブ(lntematiorlal Coral Reaf lnitiative)の略称。1994年に発足した、サンゴ礁の保全と持続可能な利用に関する包括的な国際的枠組み。1)沿岸管理、2)能力養成、3)研究・モニタリング、4)再検討が活動の4本柱となっている。1995年にフィリピンでICRI会合が開催され、「行動の呼びかけ」「行動の枠組み」を採択。その後の活動の指針とする。事務局と企画調整委員会(ICRI-CPC:ICRI Coordination Planning Committee)で運営されている。2005年から2007年は、日本とパラオが共同事務局を担当。
胃腔 - ロからつながる袋状の組織で、胃の内腔。
胃層 - 胃腔の表面を覆っている細胞層。
磯焼け - 低塩分などの影響で海藻類が岩礁から消滅する現象。
一斉産卵 - 初夏の満月ごろの日没後に、多くのサンゴ種が一斉に卵と精子を放出して、海水面で受精する有性生殖の形態。
- イノー
- 沖縄の方言で、サンゴ礁の礁原に発達する礁池や内湾などの静隠な浅い水域のこと。
- インタープリテーション
- 一般的には「通訳」のことを言うが、ここでは、自然と人間のあいだの通訳、すなわち、自然の発するメッセージを分かりやすく人々に伝え、自然とのふれあいを通じて喜びや感動を分かちあおうとする「解説活動」のことを指す。
渦鞭毛藻 - 2本の鞭毛を持つ単細胞の藻類で、細胞には横溝を有する。サンゴ類などに共生している褐虫藻はGymnodinium属の渦鞭毛藻で体外では鞭毛をもつ。
栄養塩 - 海水や陸水に含まれ、植物プランクトンや藻類の栄養になる物質。硝酸塩・亜硝酸塩・アンモニウム塩・リン酸塩・ケイ酸塩など。栄養塩が過多になると、植物プランクトンや藻類の異常発生が起こり、生態系のバランスが崩れる。また、栄養塩過多はサンゴの骨格形成を阻害することも知られている。
- エコツアー
- 森歩き、山登り、沢登り、カヌー、ダイビングなど、自然にやさしい活動を行いながら、自然を学び楽しむ体験型ツアー。
SPSS - 海底質中懸濁物質含量(corltents of Suspended Particles in Sea Sediment)の略称。海域の赤土汚染をモニタリングする簡便な手法として1985年に沖縄県衛生環境研究所で開発された。海底から土砂を採取し、容量内で懸濁させた時の透視度から懸濁物質(赤土等)の量を推測する。
枝状 - (造礁サンゴにおいて)棒状の群休から幾重にも枝が分岐した群体の形状。
エプロン礁 - 岬部を囲むように発達する小規模なサンゴ礁で、礁池を欠<。
横隔板 - 莢の下部の空所が成長にともなって竹の節目のように仕切られた構造体。
沖縄県オニヒトデ対策会議 - 沖縄県自然保護課が事務局になり2002年に発足したオニヒトデ対策を目的とした会議。発生状況の調査、簡易調査マニュアル、駆除戦略などを環境省、市町村、関係機関からなるメンバーと検討する。
溺れ谷 - 陸上で形成された谷が海面上昇などよって沈水したもの。
か
海岸段丘 - 少なくとも第四紀以降隆起傾向にある、または隆起傾向にあった地域の海岸沿いにみられる段状を呈する平坦な地形面(群)。
塊状 - (造礁サンゴにおいて)塊状の群体の形状。典型的には半球形になる。
海食崖 - 波食作用によって形成された海崖。
海食棚 (波食棚)- 波食作用によって形成される潮間帯の平坦な地形。
海成層 - 海面下(海底)で堆積した堆積物の総称。
海成段丘 - 過去化海面下(海底)で形成された平坦面が、断続的に離水する過程を経ることによって形成されていく段状の地形面(群)。海岸段丘とほぼ同義であるが、海成段丘という言葉はその成因を伴っている。
撹乱 - サンゴ群集の内外からさまざまな力(撹乱要因)が加わって、群集の様相を変えること。オニヒトデによるサンゴの捕食や、台風時の波浪による物理的な破壊などがある。
火山深性複合岩体 - 火山岩と深成岩が混在している岩体。
活性酸素 - 原子核の周りの電子数が変化して不安定になった酸素で、酸化力が強<、他の原子や分子から電子を奪い取る性質がある。
活性状況 - 機能が出現したり、効率が向上したりすること。また、反応や応答をする能力。サンゴの場合、成長量などの活性状況から健康状態を判断できる。
褐虫藻 - サンゴに共生する直径10ミクロン程の単細胞の渦鞭毛藻の一種。光合成を行ってサンゴに酸素と栄養を供給している。
合併浄化槽 - 屎尿(しにょう)と生活雑排水をあわせて処理する浄化槽。屎尿のみを処理するものは単独浄化槽。
加入量 - 生物群集に対して新たに加わる生物の量。
地形 - 石灰岩でできている地域が侵食や風化を受けてできた特有な地形。炭酸を含む雨水に溶水されやすいため、窪地や石灰洞を形成する。
環礁 - 中央に深い礁湖を持った環状に配列したサンゴ礁で、日本周辺海域には見られない。南北大東島は環礁が隆起して形成された(隆起環礁)と考えられている。
共生 - 異なる種の生物が共に住んで緊密な関係を成立させることで、互いに利益を得ることが多い。褐虫藻は造礁サンゴの組織内部に共生するため、共生藻とも言われている。
共生関係 - 異種の生物が共存する関係。普通、二種の生物が互いに利益を交換して生活する相利共生をさす。
共生藻 - 造礁サンゴやシャコガイなどの体内に共生している微小な藻類で、造礁サンゴの場合は褐虫藻がこれにあたる。
裾礁 - 島の周りを縁取るようにして発達するサンゴ礁の形態で、日本の多くのサンゴ礁はこれに当たる。
- クチャ
- 主として沖縄中南部、宮古島に分布する島尻層群泥岩の沖縄方言名。風化しやすい。
国頭 - 沖縄島北部、久米島、石垣島、西表島に分布し、砂岩、泥岩、千枚岩、砂礦層などを母材とする赤黄色土壌。酸性を示す。
- グリーンベルト
- 土砂流出を防ぐため、畑の周囲に植えられた植物の帯。石垣島では月桃(沖縄の島々の山野に白生する、ショウガ科の多年草)を植えている。
- グレージング
- 草食動物が植物をかじって食すること。
黒帯病 - Black Band Disease。1970年代から世界の造礁サンゴで見られるようになった病気。原核生物のシアノバクテリアが原因菌で、これに硫酸還元菌や硫化物酸化菌が加わったマット状の黒い帯となって組織の壊死が広がっていく。
群集 - ある場所に存在している生物個体群の集合体。
群集構造 - 群集とは種の組成をもとにして分けられた植物群落の分類単位で、群集構造は群集の種組成を意味する。本来は植物に用いられる用語だが、分布のしかたが植物と似ているサンゴにも流用されている。
群体 - 共通の親個体から出芽によって形成されたポリプの集まりで、出芽後も離れることなく複数のポリプが共肉部で連絡してできている状態。
群落 - 生物群集の意。植物社会学的には特定の組成を持った群集を優占種の名を冠して表現する(例:ススキ群落)。
光阻害 - 強い光の影響で光合成活動が阻害される現象。
高島 - 大陸島や火山島など、山地からなる島。
勾配修正 - 畑からの土砂流出を防ぐため、畑の勾配を緩やかにすること。
光量子量 - 光のエネルギー量を表す最小単位。
さ
対州層群 - 長崎県対馬に分布する第三系で、デルタ成?漸深海成堆積物から構成される。
栽培漁業 - 水産対象種の種苗を人の手でじっくり育てて放流し、成長したものを漁獲する漁業。
サンゴ群集 - サンゴ類が一つの場所に多数生育して形成する集まりで、サンゴ礁の様々な環境によって群集を形成する主要な種の群体形が異なる事が多<、異なる景観が作り出される。
サンゴ群体 - 共通の個体から出芽によって形成されたポリプの集まりで、出芽後も離れることなく複数のポリプが共肉部で連絡してできている状態。
サンゴ群落 - サンゴ群集。ある場所の瀬即する複数種のサンゴ個体群の集まり。
サンゴ個体 - ポリプの骨格。
サンゴ礁群集 - サンゴ類に限らず、サンゴ礁生物がある場所を占めて生息し、さまざまな関係を成立させている生物の関係。
サンゴ礁段丘 - 海成段丘の1つの形態。過去に形成されたサンゴ礁が不連続に離水していくことで形成される。
サンゴ相 - ある地域のサンゴの種類数と種類組成。生息する種類数が多い場所は、サンゴ相が豊富な場所という。
サンゴ体 - サンゴの骨格、群体サンゴの場合はサンゴ個体と共骨のすべて。
GIS - Geographic lnformation SyStem。地理情報システム。地理的なさまざまな情報に関連づけなどの処理を行い、データ化された地図上として視覚的に表示するシステム。
GCRMN - 地球規模サンゴ礁モニタリングネットワーク(Global Coral Reaf Monitoring Network)の略称、ICRIのブログラムの一つであり、サンゴ礁モニタリングを実施する人々や政府機関、研究機関、NGO及びサンゴ礁の利用者によるネットワークである。持続的な利用のためのサンゴ礁のモニタリングを推進している。IOC-UNESCO、IUCN、世界銀行、UNEPの4つの国際機関からの資金提供を受け、科学技術諮問委員会(STAC)の指導のもとに戦略計画にのっとって運営される。1998年以来、地球規模のネットワ一クを通じて、2年に一回、世界のサンゴ礁の現状報告を発行している。
GPS - Global Positioning System。全地球無線測位システム。多数の衛星から発射された時刻信号の電波の到達時間などから,地球上の電波受信者の位置を三次元測位するシステム。カー・ナビゲーション・シスムなどに利用されている。
自然侵食 - 地表が自然現象により削り取られること。雨食一河食・雪食・水食・風食・波食などがある。
資源保護 - 自然から得られる産業の基となる要素(地下資源・水資源・海洋資源・水産資源・人的資源・観光資源など)を、永く利用できるように守っていくこと。
被覆状 - 基盤を覆うように被服して成長した群体の形状。
刺胞動物 - 餌を捕ったり攻撃したりするのに用いる刺胞という細胞器官をもった動物で、サンゴ、クラゲ、イソギンチャク、ヒドラなどが含まれる。
島尻層群 - 琉球列島に広く分布する第三系堆積物。主に大陸由来の砂泥から構成されるが、一部凝灰岩も侠在している。
島尻マージ - 主に沖縄島南部、宮古島に分布し、琉球石灰岩を母材とする暗赤色土壌。アルカリ性を示す。
- ジャーガル
- 主に沖絹烏中南部、宮古烏に分布し、烏尻層群泥岩(クチャ)を母材つる灰色土壌。アルカリ性を示す。
種間交雑 - 異なる遺伝子をもつサンゴ群体の精子と卵子が受精して起こる受精形態。
樹枝状 - (造礁サンゴにおいて)柱間隔が広く樹の枝や鹿の角を思わせるような群本の形状。
種多様性 - 種類の多さや複雑さなどの性質。
種多様度 - 種の多様性の高さを示す尺度。種数で表す場合をはじめ、さまざまな指数が考案されている。
出芽 - 群体が成長していく際に、ポリプが目を出すようにして新たに形成されること。
種苗 - 水産学用語では、養殖のための稚魚や卵をさす。植物の苗も種苗である。
種苗放流 - 卵から育てた水産対象種の稚仔を種苗といい、この種苗を放流すること。
準平原 - Davis.W.M.によって提唱された侵食輪廻の最終地形で、波状小起伏の広域侵食面。
礁縁 - 外礁の外側礁原でサンゴ礁の縁辺部。
礁原 - サンゴ礁の上面の平坦な部分で、岸から礁湖をはさんで遠く離れた外礁では、小潮にも干上がるサンゴがほとんど生育しない内側礁原 inner flat、外側礁原 outer flat からなる。
礁湖 - 堡礁と陸の聞や環礁の中央部に発達する深い水域。
礁斜面 - サンゴ礁の礁縁部から傾斜して落ち込んだ部分。
造礁サンゴ - 組織内に褐虫藻を共生させて、炭酸カルシウム骨格を形成して成長するサンゴ。
礁池 - 裾礁の礁原に発達する水域で、水域は浅く、干潮時には外洋から離れることが多い静穏で繊細な群体形のサンゴが生育し、海草帯などが発達する。
上布の海晒し - 苧麻(ちょま)の繊維を細く紡いだ糸で織った上質の麻繊維の上布を作る過程で海に晒すこと。八重山に伝わる伝統技術。
礁舗 - 礁嶺陸側のサンゴ礫やサンゴの分布する高まり部分。
礁嶺 - 外礁の内側礁原の高く盛り上がった場所で、長時間干上がるために生物があまり豊富でない場合が多い。
- シルト
- 粘土よりも粗粒、砂よりも細粒の粒子で、粒径は1/16?1/256mm。
侵食小起伏面 - 侵食輪廻における老年期に形成される起伏の小さい侵食面。
- スキューバ、スクーバ
- SCUBA(self-contained underwater breathing apparatus)自給気式潜水装置の略称。圧搾空気をつめたボンベを背負い、圧力自動調節器を通してマウスーピースから呼吸するもの。
州島 - 礁性砂礫から構成される小規模な低島。
生活環 - 世代ごとに繰り返される季節の変化に関連した発生や成長の過程。生活史と同義で単に生物の一生を指す場合もある。
石灰化 - 生物による炭酸カルシウムの生産。サンゴ類、貝類、有孔虫類、石灰藻などが行う。
石灰岩堤 - 石灰岩地域の崖沿いに発達する堤状の高まり。
石灰質 - サンゴの骨格や貝殻などの主成分になっている炭酸カルシウム(CaC03)。
- セディメントトラップ
- 懸濁物質の沈殿量を測定するために工夫される筒状の器具。
石花海海盆 - 駿河湾の海底に位置する最大水深1000m程度の凹地。
造礁(性) - 組織内に裸虫藻を持っている状態で、造礁サンゴは全て共生藻として褐虫藻を持っている。
- ソフトコーラル
- 広義のサンゴの中で石灰質の骨格を持たないグループ。
た
台礁 - 大陸棚などに発達する比較的大規模なサンゴ礁で中央に浅礁.湖(礁池)をもつ。深い礁湖はみられない。
堆積岩 - 堆積物が沈積し、物理的・化学的作用によって固化した岩石。
- タイドプール
- 干潮時に磯にできる潮溜まり。
卓礁 - 田山利三郎によって提唱されたサンゴ礁の一類型。孤立して発達する小規模なサンゴ礁で浅礁湖(廻流)をもたない。
卓状 (テーブル状)- 横方向に発達した板状の部分を中央の軸で支えている、テーブル状の群体の形状。テーブル状、板状ともいう。
段丘崖 - 複数の段丘を境する急度。
暖水塊 - 周囲の水温よりも暖かい水塊。
断層崖 - 断層によって生じた急度。直線的な場合が多く、主に空中写真などで判別される。
柱状 - (造礁サンゴにおいて)基盤からほぼ直立する柱状の群体の形状。
沖積土壌 - 河川によって運ばれてきた土砂が堆積してできた土壌。
潮間帯 - 高潮線(満潮線)と低潮線(干潮線)に「まさまれた部分で、干潮のときには大気中に出て、満潮時に海中に没する。
沈降海岸 - 海面の高度変化よりも、地盤が沈降することによって形成された海岸地形。
沈水カルスト地形 - カルスト地形が海面の上昇などによって沈水したもの。
泥岩 - 粒径1/16mm以下の粒子によって構成される堆積岩
低島 - 急峻な山地などが存在せず、全体的に低平な台地からなる島。
テーブル状 (卓状)- 横方向に発達した板状の部分を中央の軸で支えている、テーブル状の群体の形状。テーブル状、板状ともいう。
- テクトニクス
- 地球の大規模な構造と変動について研究する学問。
- トラフ
- 海底の地溝で、水深が5000mに満たないものを指す。水深が5000m以深に及ぶものは海溝と呼ばれる。
- ドリーネ
- カルスト地形の1つで、径10?1000mの円ないし楕円形の輪郭を持ち、深さ2?100m程度の溶食凹地形である。
な
軟組織 - サンゴの骨格を除く生きた部分。
沼層 - 千葉県館山市周辺に分布するサンゴ化石を含む完新世堆積物。縄文海進時に溺れ谷となった一帯に造礁サンゴが生息し、それらが後に隆起し陸上に現れた地層。
- ノッチ
- 石灰岩で構成される海塵などに発達する窪み状の小地形で、生物侵食や化学的・物理的侵食によって形成される。水平的に連続したノッチの後退点は海面指示者として有用である。
は
- バイオテクノロジー
- 生物をエ学的見地から研究し、応用する技術。近年は特に、遺伝子組み換え・細胞融合などの技術を利用して品種改良を行い、医薬品・食糧などの生産や環境の浄化などに応用する技術をさす。
白痘 - White Pox。1996年以降、カリブ海を代表する枝状のサンゴ(Acropora palmate)の90%を殺し、絶滅危惧種に追いやった恐るべき病気。最近、人畜の腸内細菌であるセラチア菌が原因菌であることが特定されたため、屎尿排水の影響が問題視されている。
白化 - サンゴやシャコガイなどは体内に褐虫藻が共生しており、光合成を行う褐虫藻から酸素と栄養をもらって生きている。高水温などが原因で体から茶色の褐虫藻が抜け出した結果白くなる現象を白化と言う。サンゴなどは白化が長く続くと死んでしまう。
発生 - 受精卵や無性的に生じた芽などが成長する過程。
- パッチ(状)
- 浅海域に発達した小さな斑状のサンゴ眺のような形状。
浜下 り- 旧暦三月三日の春の大潮の日に浜に出て潮干狩などを楽しむ沖縄の伝統的行事。
- パヤオ
- 沖合いに設置される人口浮漁礁の―穫で、沖縄小笠原などで漁場として利用される。
干瀬 - 沖縄の方言で、サンゴ礁で干潮に干上がる礁干のこと。
被度 - サンゴなどの固着生物が基質を被覆する面積の割合。
- フーカー
- 船上のコンプレッサーからホースを通して水中に圧搾空気を送り、マウスーピースから呼吸する潜水装置。スキューバより長時間の潜水が可能。
- プラヌラ
- サンゴの幼生、泳ぐことができる。
プランクトン生活 - 水中での浮遊生活。魚類やベントスも生活史のある時期プランクトン生活を営む。
扁形動物吸虫類 - 扁形動物門は左右相称動物の中で体制が最も簡単な動物群で、背腹に平たく、楕円形や細長い形をしている。このうち吸虫類は動物に寄生して血液等を吸って生活するグループ。
保育型 - 体内受精をして、ポリプの胃腔内でプラヌラ、まで保育する有性生殖の型。ハナヤサイサンゴ科で普通にみられ、ポリプは幼生を放出する。
堡礁 - 島から遠く離れ一定の距離を置いて発達するサンゴ礁で、島との間に深い水域がある。日本では石西礁湖のみで見られる。
放卵放精 - 初夏の満月ごろの日没後に、多くのサンゴ種が一斉に卵と精子を放出して、海水面で受精する有性生殖の形態。
堡礁 - 島から遠く離れ、一定の距離を置いて発達するサンゴ礁で、島との間に深い水域がある。日本ではほとんどみられない。
- ホットスポット
- 地表の一箇所に継続的にマグマが供給される場所。位置はプレートの動きに関係なく一定である。
- ポリプ
- サンゴの基準単位。イソギンチャク様の動物とその骨格からなる。
- ホルンフェルス
- 接触変成作用によって生じた変成岩の一種。圧力などよりも温度が主要な変成条件と考えられている。
ま
- マイクロアトール
- 干出のための群体上部の中央部が死亡し、周辺部分が生きている群体の形状で、微小な環礁に見立てた呼び名。
宮良層群 - 八重山諸島に分布する始新統で、石灰岩を主とする宮良川層とグリーンタフである野底層からなる。宮良層群は極浅海相で、変成作用は受けていないが、断層運動によって傾動地塊化している。
無性生殖 - 配偶子を用いずに、子孫を増やす営み。無性生殖によってできる個体は、遺伝子組成が等しいクローンである。
- モニタリング
- 環境や生物の状態を監視すること。
や
八重山地区 オニヒトデ対策連絡会議 - 八重山地域におけるオニヒトデの発生状況等の情報を共有するとともに、地域としての対策を検討するために開催されている会議。八重山漁業協同組合、八重山ダイビング協会、沖縄県、沖縄県八重山支庁、石垣市、竹富町、西海区水産研究所、県水産試験場八重山支場、沖縄県環境科学センター、WWFジャパンサンゴ礁研究センター、日本ウミガメ協議会、(有)海游、八重山環境ネットワークなどが参加。
八重山変成岩 - 八重山諸島に分布する、上部古生界のトムル層と上部中生界の富崎層からなる変成岩類。変成作用の時期は、トムル層がジュラ紀、富崎層が古第三紀とされる。トムル層は藍閃石片岩相の高圧型変成岩類、一方、富崎層は千枚岩・チャートからなる弱変成岩類である。
有性生殖 - 卵と精子など配偶子を用いて、子孫を生産すること。有性生殖によってできる個体は、遺伝子組成が異なっている。
葉状 - (造礁サンゴにおいて)基盤から遊離して伸びる薄く幅広い群体の形状。
ら
- ラグーン
- 礁湖と同義。
陸棚礁 - 大陸沿岸や陸島部で形成されるサンゴ礁。
離礁 - 内湾的環境の浅海域に発達する大小様々な形状の小さな斑状のサンゴ礁。
離水サンゴ礁 - 過去数千年間において形成されたサンゴ礁が、海水準低下あるいは陸地の隆起などの原囚によって現海水準上に現れているもの。
離水卓礁 - 離水サンゴ礁の1つの形態で、卓礁が離水したもの。
隆起環礁 - 海洋プレート上で形成された環礁が、プレートの移動に伴って沈降し、海溝周縁隆起帯に達したところで隆起に転じ、陸上に現れたもの。日本では、大東諸島がこれに相当する。
隆起サンゴ礁 - 離水サンゴ礁のうち、その成因が隆起であることが明らかなもの。
琉球石灰岩 - 第四紀更新世に琉球列島周辺海域において堆積したサンゴ礁性石灰岩。
琉球層群 - 琉球列島に広く分布する更新統の総称。石灰質堆捕物(琉球石灰岩など)が主体であるが、非石灰質堆積物(国頭礫層など)も含まれている。
礫 - 粒径が2mm以上の粒子の総称。これらは粒径によって細礫(2?4mm)、中礫(4?64mm)、大礫(64?256mm)、巨礫(256mm以上)に区分される。