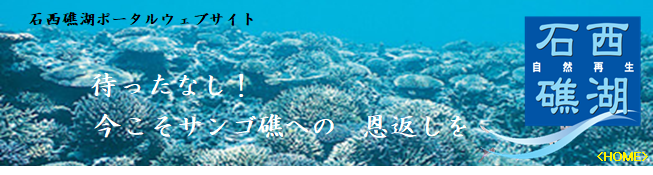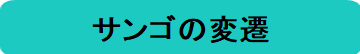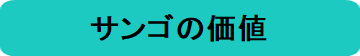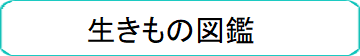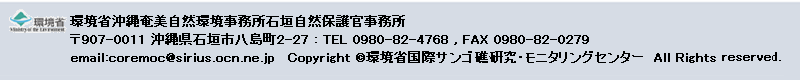石西礁湖生きもの図鑑ーウニ・ナマコ・ヒトデのなかま

|
種名:オニヒトデ 学名:Acanbaster planci 輻長(体の中心から腕の先までの長さ)は15cm程度。 多数の腕と、全身に生えた棘が特徴。サンゴ礁のいたるところで見られる。棘には毒があり、刺されると刺された部分を中心に激しく痛む放散痛があり、人によってはアナフィラキシーショックによって最悪死に至ることもある。 サンゴを食べることが有名だが、小さい稚ヒトデの時は石灰藻のサンゴモや岩の上の有機物を食べ、大きくなるとサンゴを食べるようになる。 食べるときは口から胃を吐き出してサンゴに被せ、直接当てて消化、吸収する。また、サンゴの中でもミドリイシ属やコモンサンゴ属のサンゴを好み、ハマサンゴ属のサンゴはあまり食べない。 本種は琉球列島の各地で度々大量発生しており、サンゴが食害を受けているが、はっきりとした発生原因は分かっていない。各地域でダイバーらによる駆除活動が積極的に行われており、獲って陸に上げる、水中で体の中心を必ず切るように4つに切断、薬品を直接注入するなどしている。陸揚げされたオニヒトデは、廃棄されるか、細かくして肥料にされるなどして利用されている。 ホラガイやフリソデエビなどの捕食者が天敵だがオニヒトデのみを食べているわけではないため、大量発生防止にはあまり効果はない。 |
 有害生物
有害生物
 有毒生物
有毒生物
|